
Close

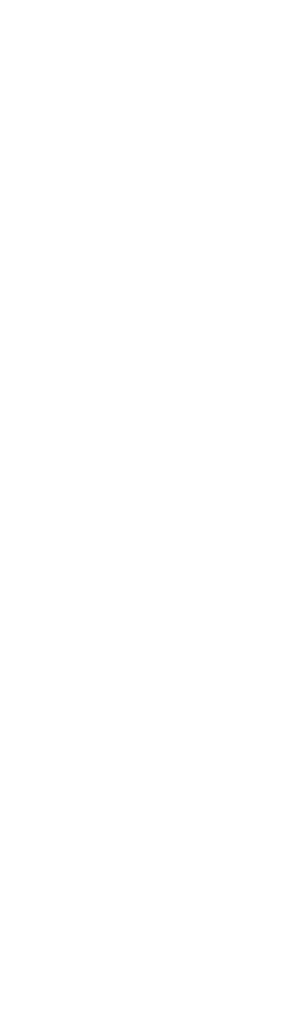
静かな山あいの町、長野県木曽平沢。
古き良き街並みが残る奈良井宿のほど近くに、漆の伝統を受け継ぐ「まるなか漆器店」があります。
漆器の産地として長い歴史を持つこの町は、今もなお漆とともに生きる職人たちの手しごとが息づいています。
代々受け継がれてきた技術と想いを大切に、ひとつひとつの器に向き合いながら、今の暮らしに寄り添う漆器づくりを続けています。
天然の素材を用い、機械では扱えない繊細な工程を重ねて生まれるその器は、丈夫で、修理を重ねながら永く使い続けることができます。
美しく、機能的でありながら、日本文化の奥深さを感じていただける漆器。
使い込むほどに表情を変え、深みを増していく様は、まるで使い手とともに歳月を重ねていくようです。
その変化を愛し、育てることもまた、漆器の大きな魅力です。
どうぞ、木曽の地に根づくものづくりの息吹を、手にとってお確かめください。

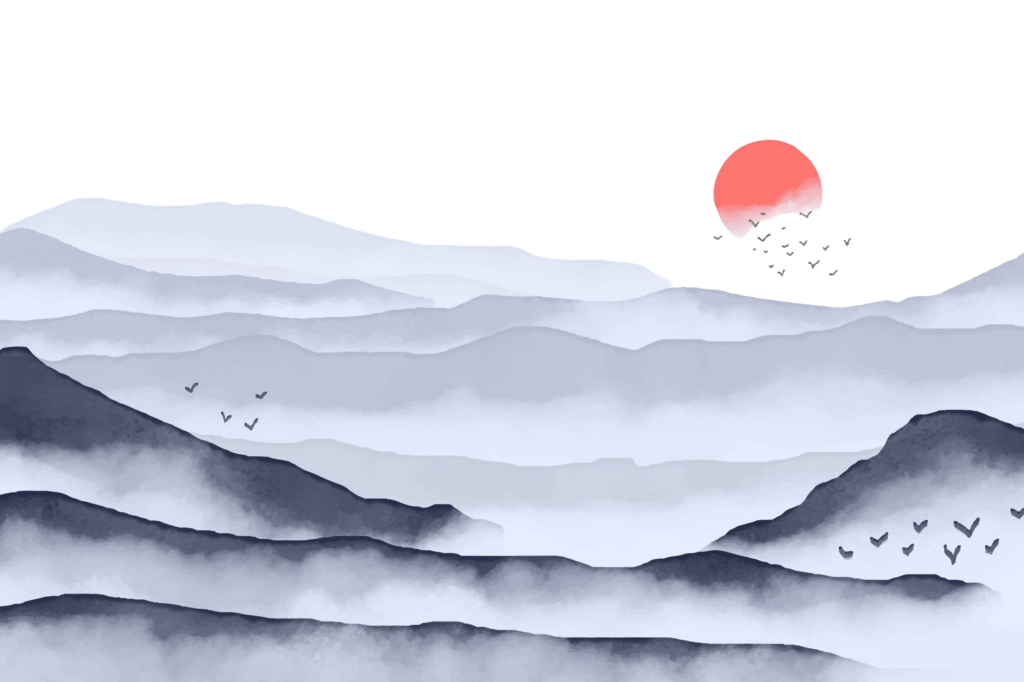












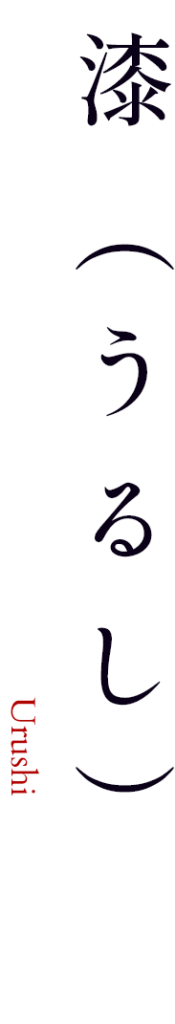
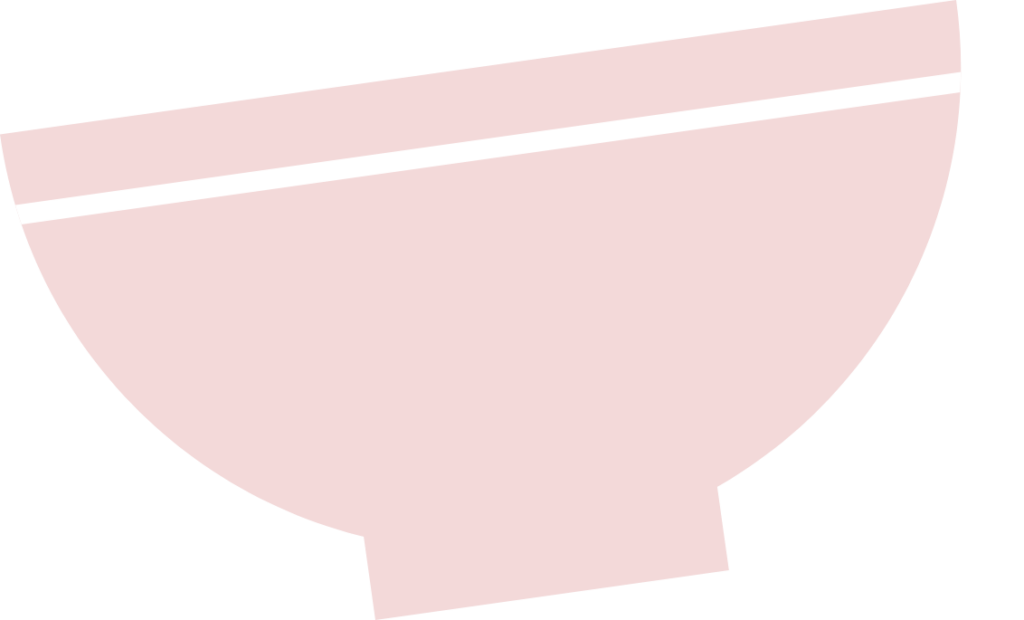

漆は、一本の木からごくわずかしか採れない天然の樹液で、採取には高い技術と時間を要します。自然由来であり、抗菌性・耐水性・耐久性に優れ、古くから日本の生活に根ざした素材です。
漆を吉野紙で漉し、塵などの不純物をとりのぞく工程「漆漉(こ)し」を行います。
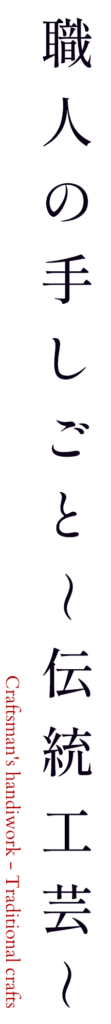

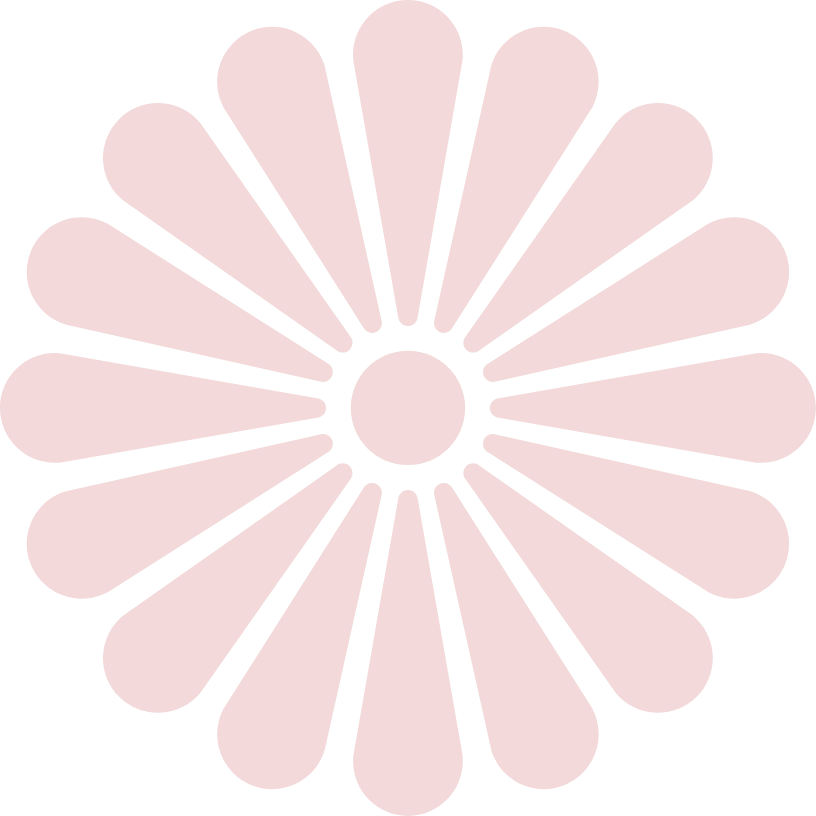
木曽漆器は、長野県・木曽平沢で育まれてきた伝統工芸です。職人が気温や湿度を精緻に管理しながら、木曾の地で受け継がれる伝統技法である蒔絵や沈金、堆朱などの塗り技法により一つひとつの工程を丁寧に制作しています。天然素材にこだわり、作成品と対話しながら時間をかけて完成した漆器は、その存在に格調と個性を与えます。
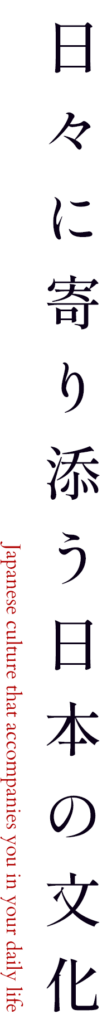

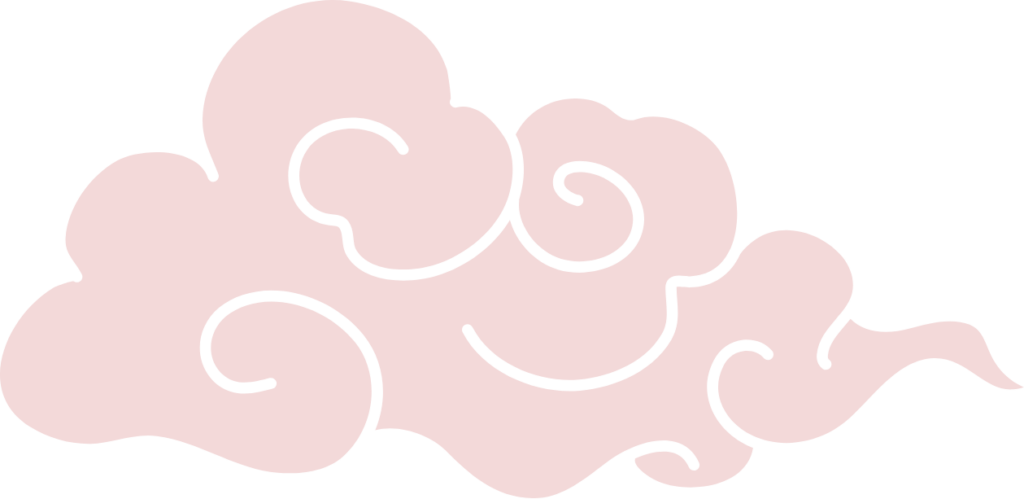
漆器は、日本人の生活や文化に古くから深く関わってきました。太古の昔より日々の食卓や節目の所作を彩り、人々の心に寄り添い続けてきました。伝統技法も継承しつつ現代の暮らしに溶け込む器、お盆、花器などをデザイン・創作しています。漆器の美しさ多様な表情は昔も今も日常を豊かに彩ります。天然素材から生まれ、やがて自然に還る循環する和のうつわ。漆器は人と人との絆、過去から未来へのつながりを象徴する輪の器です。

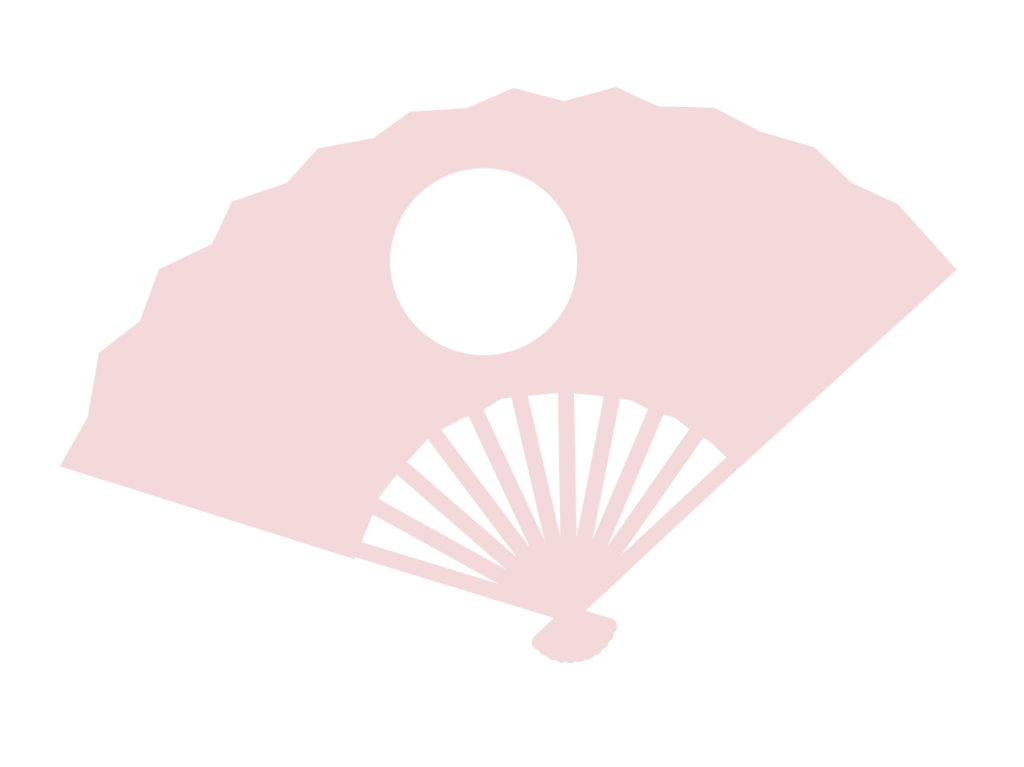
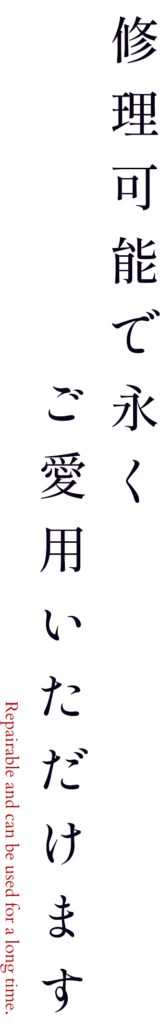
漆器は塗り直しや修理ができるため、使い込む中で傷がついても再生が可能です。塗り直しによって現代の暮らしに合った装いに仕立て直すこともでき、持ち主とともに時間を重ね、世代を越えて受け継がれていく器となります。
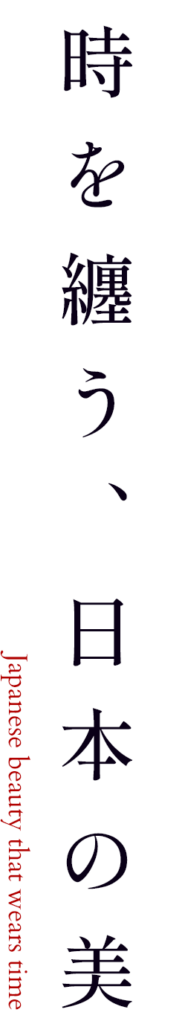


漆は、時とともに透明感と艶を深め、独自の風合いへと変化していきます。使うほどに味わいが増し、器は単なる道具から「時を纏った存在」へ。日本の美意識が息づく漆器は、過去と現在、そして未来をつなぐ文化のかたちでもあります。